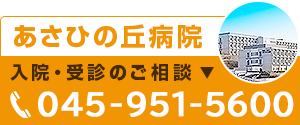あさひの丘病院で行っている専門診療についてご紹介します。
※診療項目をクリックすると詳細が表示されます
クロザリル
クロザリル(クロザピン)とは
クロザリル(一般名:クロザピン)は、今まで複数の抗精神病薬による治療を受けてきたにもかかわらず、症状が十分に良くならなかった難治性の統合失調症の患者様に効果が認められた薬です。日本では2009年に認可されています。
対象となる患者様
- 抗精神病薬を2種類以上、十分量・十分な期間内服したが症状の改善がない、または不十分な場合。
- 抗精神病薬2種類以上で副作用により増量ができない場合
クロザピンの効果
下記の改善が期待できます。
- 幻覚や妄想の改善
- 認知機能の改善
- 攻撃性や暴力の改善
主な副作用
クロザピンは有効性の高いお薬ですが、他のお薬以上に副作用に注意が必要です。
- 顆粒球減少症
- 心筋炎
- けいれん
上記のような副作用があり、最も注意しなければいけないのは顆粒球減少症です。
顆粒球減少症とは
細菌などから体を守る白血球の中の顆粒球(好中球)が減ってしまうため、感染症を起こしやすくなります。
そこで、患者様が安心してクロザピンを飲んでいただくために、定期的に血液検査を行います。また、当院では聖マリアンナ医科大学病院の血液内科とも連携しています。
モニタリングシステムについて
クロザピンによる治療を安心して受けていただくために、クロザリル患者モニタリング・サービス(【CPMS】と呼ばれています)という第3者機関に血液検査を報告することが義務づけられておりクロザピン適正使用委員会による承認後、クロザピンは処方可能となります。
クロザピンの管理体制
クロザピンの治療は、国により流通管理と安全管理のための「クロザピン適正使用委員会」の設置が義務付けられています。日本では、この委員会が認可した医療機関と許可を受けた医師のみが処方できます。当院は、登録医と研修を修了した看護師・薬剤師などの多職種連携チームによるクロザピン治療を実施している医療機関です。
クロザピンによる治療流れ
当院では登録医とそのほか研修を修了した看護師・薬剤師等の多職種連携チームでクロザピン治療を実施している医療機関です。
当院での取り組みについて
クロザピンの処方は、事前に効果や副作用を丁寧に説明し、同意を得た上で行います。安全に服用できるよう、定期的な血液検査でモニタリングを実施します。
また、医師、看護師、精神保健福祉士、臨床検査技師、薬剤師などの多職種連携チームが、患者様とご家族をサポートし、安心して治療を継続できるよう支援します。
LAI(持続性注射剤)
LAI(持続性注射剤)とは
LAIとは、Long Acting Injectionの略で、統合失調症の治療で用いられる、お薬の効果が長く続く注射剤のことです。 持効性注射剤といい、1回の注射で数週間から3か月にわたり、効果が続きます。 その間は、飲み薬でどうしても起こってしまう、飲み忘れによるお薬の効果の減弱などを防ぐことができます。
当院では、社会生活を送りながら薬を継続して服用するのは難しいことだと考えています。
そのため、安定して薬の効果が得られるLAIでの治療を積極的に行っています。
- 28日に1回
- 3か月に1回
2種類があります。
統合失調症はお薬による治療を続けることで症状を抑えることができます
統合失調症は、適切な服薬と生活環境の調整で症状をコントロールできます。症状とうまく付き合えるようになれば、薬の量を調整しながら社会生活を送ることも可能です。
しかし、自己判断で服薬を中断すると再発のリスクが高まり、再発を繰り返すことで症状の悪化や社会生活への影響が生じる可能性があります。
再発を繰り返すときの変化
- 病気がだんだん治りにくくなる
- 脳の働きが回復しにくくなる
- お薬が効きにくくなる
- 患者さんご自身の自尊心が傷つく
- 失業したり、休学が必要となることがある
- ご家族やお友達などを悲しませる(心配させる)
再発を防ぐには、治療を続けてお薬をやめないことが大切です
統合失調症の治療には長い年月がかかります。その間に自分で判断して途中でお薬をやめると再発する可能性が高くなります。きちんと治療を続けることが大切です。
お薬を正しく服用すると入院する割合が低くなることがわかっています。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止または浅くなる状態を指し、睡眠の質を著しく低下させます。その結果、日中の強い眠気や集中力の低下、さらには高血圧や心疾患などの健康リスクを引き起こすことがあります。
高齢者ではこのような睡眠障害の頻度が高く、また、うつ病の患者様でも睡眠障害は代表的な症状の一つです。さらに、睡眠不足や質の悪い睡眠は認知機能の低下と深く関わっており、認知症のリスク因子ともされています。
CPAP療法とは?
CPAP(シーパップ)療法とは、「持続陽圧呼吸療法」とも呼ばれる、睡眠時無呼吸症候群の一般的な治療法の一つです。睡眠中に専用のマスクを装着し、気道に一定の空気圧をかけることで、気道が閉塞しないよう保つ仕組みです。
この治療により、無呼吸を防ぎ、睡眠の質を向上させることで、日中の眠気や集中力の低下といった症状の改善が期待できます。治療中は、定期的な診察で治療効果を確認し、必要に応じて調整を行います。
当院の取り組み
当院では、睡眠時無呼吸症候群の検査およびCPAP療法を導入いたしました。対象は通院・入院中の患者様で、以下のような方が検査の適応となります:
- 日中の眠気や集中力の低下がある方
- 睡眠中にいびきがある、または肥満傾向のある方
- 高齢者で不眠などの睡眠障害がある方
- うつ病をお持ちで睡眠に問題がある方
検査は入院にて行い、機器の装着・取り外しはスタッフがサポートいたしますので、安心して受けていただけます。検査結果をもとに医師が重症度を評価し、最適な治療法をご提案いたします。
今後も患者様が快適な生活を送れるよう、スタッフ一同、継続的な治療支援に努めてまいります。
修正型電気けいれん療法(m-ECT)
m-ECT(修正型電気けいれん療法)とは
m-ECTとは、「修正型電気けいれん療法(modified Electroconvulsive Therapy)」の略で、静脈麻酔と筋弛緩薬を併用し、患者様が眠っている間に安全に行われる電気けいれん療法(ECT)です。額やこめかみに数秒間電気を流し、脳内に人工的な発作を誘発することで、さまざまな精神症状の改善を目指します。
従来のECTと異なり、けいれんの激しい身体反応を抑え、麻酔科医による全身管理のもと、安全に実施できるよう進化した治療法です。神奈川病院では令和6年10月よりm-ECTを導入し、重症のうつ状態や治療抵抗性の精神疾患などに対応しています。
m-ECTが有効な症状・疾患
m-ECTは以下のような重症度が高い、または薬物療法で効果が乏しい精神疾患に有効とされています。
- 重度のうつ状態(特に難治性・自殺念慮の強いケース)
- 統合失調症(幻覚妄想・興奮・昏迷状態など)
- 双極性障害(躁状態・うつ状態)
- 急性錯乱状態や幻覚妄想を伴う状態
- 拒食・絶飲など、身体的リスクを伴う精神状態
- 強迫症、統合失調感情障害 など
当院では、入院患者様を対象に、精神科専門医の判断に基づき施行しています。
副作用・リスクについて
m-ECTは「電気ショック療法」という旧来のイメージとは異なり、現在は非常に安全性の高い医療行為です。薬の副作用が出やすい高齢者でも適応されることが多く、むしろ薬物療法よりリスクが低い場合もあります。
副作用としては、治療後の頭痛や筋肉痛、一時的な記憶障害が挙げられますが、多くは一過性で自然に回復します。治療内容や副作用については、事前に丁寧な説明を行い、納得いただいた上で進めています。
治療期間・スケジュール
m-ECTは入院治療が原則となり、週2回の頻度で施行します。治療回数は一般的に8〜12回で、治療前後の検査を含めると、全体で約6〜7週間の治療期間を要します。た上で進めています。
m-ECTをご希望の方へ
m-ECTは即効性と高い有効性を持つ治療法ですが、すべての患者様に適しているわけではなく、十分な改善を得られない可能性もあります。
適応の有無は、精神科医による詳細な診察・診断が必要です。
ご希望の方は、まず当院の医療相談室までご連絡ください。
適切な診断と信頼できる医療環境のもと、安全で効果的な治療を提供いたします。
TMS療法(経頭蓋磁気刺激療法)
当院では、厚生労働省により保険適用が認められているNeuroStar® TMS治療装置を用いたrTMS療法を行っています。
薬物療法だけでは十分な改善が得られない中等症以上のうつ病患者様に対して、安全で効果的な新しい選択肢として提供しています。
TMS療法とは
(rTMS:反復経頭蓋磁気刺激療法)
rTMS(repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)は、専用の装置を使って頭皮上から刺激を与え、脳の活動を調整する非侵襲的な治療法です。
磁場によって脳皮質に渦電流を誘導し、うつ病に関係する神経回路を刺激・活性化させることで、症状の改善を促します。
身体への負担が少なく、意識を保ったまま治療が受けられる安全性の高い非侵襲的療法です。
2019年6月に保険収載され、当院では2024年よりNeuroStar®を導入し、専門医による治療を行っています。
当院のTMS治療(保険適応)
当院では、厚生労働省により保険適応が認められたTMS治療を実施しています。薬物療法で十分な効果が得られなかったうつ病の患者様を対象に、専門の研修を受けた医師が安全かつ適切に治療を行います。
治療対象
rTMS療法は、以下の条件を満たす成人のうつ病(大うつ病性障害)が対象です。
- 18歳以上の方
- 抗うつ薬による適切な薬物療法を受けても十分な効果が得られていない方
- 中等症以上の抑うつ症状がある方
治療は外来または入院で実施しますが、原則として入院での施行となります。治療は週5回、1回約40分、合計30回(約6週間)を目安に行います。治療は精神科専門医の指示のもと、安全管理のもとで進められます。
治療の流れ
当院では、厚生労働省により保険適応が認められたTMS治療を実施しています。薬物療法で十分な効果が得られなかったうつ病の患者様を対象に、専門の研修を受けた医師が安全かつ適切に治療を行います。
紹介状(診療情報提供書)をご用意いただき、当院外来への予約をお取りください。
当院精神科医による診察と必要な検査(心理検査・身体検査等)を行い、適応を判断します。
適応と判断された方は、入院のうえrTMS治療を開始します。
rTMS終了後は、かかりつけ医と連携し治療を継続いたします。
副作用・リスクについて
rTMS療法は副作用の少ない安全な治療法ですが、以下のような症状が一時的に生じることがあります。
- 頭皮や頭部の痛み、違和感
- 刺激部位の不快感
- 顔面のぴくつき、軽度の頭痛や肩こり
- ごく稀にけいれん発作(既往歴のある方は事前に確認いたします)
rTMS療法を希望される方へ
rTMS療法をご希望の方は、まずかかりつけの先生にご相談いただき、当院精神科外来への紹介をご依頼ください。
病状に応じて、閉鎖病棟への入院が必要となる場合もあります。治療内容や流れについては、外来担当医が丁寧にご説明いたします。